
腸活をもっと効果的にのカギは食べ合わせ!発酵食品×食物繊維で内側から健康に

1.腸活の基本!健康と美容を支える腸内環境とは?
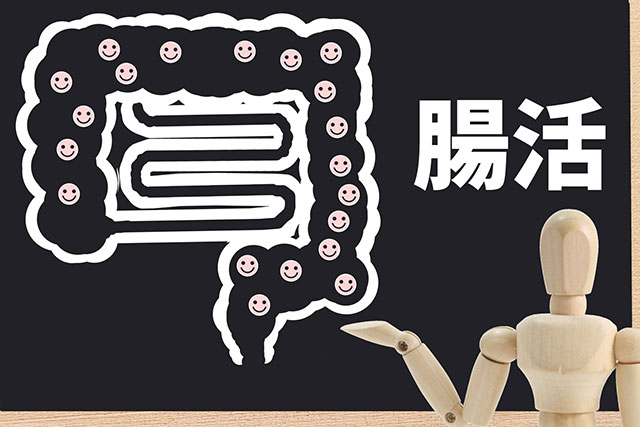
腸活とは、腸内環境を整えるために食事や生活習慣を見直す活動のことを指します(注1)。腸内には100兆個以上の細菌が生息し、その種類は500~1000種類以上に及ぶとされています。これらの細菌は働きによって身体に有用な「善玉菌」、有害な「悪玉菌」、悪玉菌と善玉菌の中間的な「日和見(ひよりみ)菌」の3つに分類され、理想的な比率は、善玉菌2:悪玉菌1:日和見菌7とされています。このバランスが崩れると、健康面だけでなく、美容にも悪影響を及ぼす可能性があると考えられています。
<腸内細菌のバランスの乱れと関りがあるとされる健康問題>
便秘、肌荒れ、肥満、糖尿病、アレルギーなど
2.腸活における発酵食品と食物繊維の重要性

腸活を実践するためには、腸内細菌のバランスを意識した食事が重要です。腸内環境を整えるために役立つのが、「発酵食品」と「食物繊維」です。
2.1 発酵食品の特徴
発酵食品には、腸内の善玉菌を増やす生きた菌が含まれています。乳酸菌やビフィズス菌が該当し、ヨーグルトや乳酸菌飲料などの発酵食品が代表です。
代表される発酵食品:ヨーグルト、乳酸菌飲料、納豆、味噌、漬物、キムチ、チーズ、お酢など
2.2 食物繊維の特徴
腸内の善玉菌を増やし、活性化させるには、そのエサとなる食物繊維を摂ることが重要です。食物繊維には水溶性と不溶性の2種類があり、それぞれ異なる役割を持ちます(注2)。
<食物繊維の特徴>
● 水溶性食物繊維:糖や脂質などの吸収速度を遅らせたり、腸内の善玉菌のエサとなります(注3)。
含まれる食材例(注4):穀類(麦類など)、果物(プルーンやレモンなど)、野菜類(オクラ・モロヘイヤ、ごぼうなど)
● 不溶性食物繊維:便のカサを増やし、腸管を刺激して腸の運動を活発化させます。
含まれる食材例(注4):穀類(玄米や全粒粉など)、きのこ類(ぶなしめじ、しいたけなど)、豆類(大豆、レンズ豆など)、野菜類(ごぼう、たけのこなど)
3.手軽に腸活!発酵食品と食物繊維の取り入れ方

腸活を実践するために、以下のポイントを意識してみましょう。
● 毎日意識して摂取する
発酵食品に含まれる乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌は、腸内に一時的にしか留まらないため、毎日習慣的に摂取することが大切です(注5)。また、食物繊維は現代の食事では不足しがちな栄養素ですので、意識的に取り入れましょう。
● 賞味期限内に食べることを意識する
発酵食品は生きた菌が含まれています。時間が経つと発酵が進み、風味や味が変化するため、賞味期限内に食べきることが大切です。
<Q&A: 加熱すると発酵食品の効果は失われるの?>
発酵食品を加熱すると菌は死んでしまいますが、最近では、死んだ菌(死菌)も体内で有用な働きをすることが明らかになっています。調理方法を工夫しながら、発酵食品を積極的に取り入れましょう(注6)。
4.発酵食品×食物繊維で腸活を効率よく!

腸活でさらに注目されているのが、「シンバイオティクス」という考え方です。
シンバイオティクス(synbiotics)とは、1999年に英国の微生物学者Gibsonらによって提案された概念で、人の体内で有益に働く生きた微生物(プロバイオティクス)とその栄養源(プレバイオティクス)となる食品成分を組み合わせて摂取する方法です。この概念は、1999年に英国の微生物学者Gibsonらによって提案されました。
発酵食品は「プロバイオティクス」、食物繊維は「プレバイオティクス」として知られています。
- プロバイオティクス: 発酵食品などに含まれる、生きて腸に届いて良い働きをする菌。
- プレバイオティクス: 食物繊維などに含まれる、腸内の善玉菌のエサとなる食物成分。
プロバイオティクスとプレバイオティクスを別々に摂取するよりも、これらを一緒に摂ることで、より強い効果が期待できるとされています。
5.実際に発酵食品と食物繊維を組み合わせてみよう!

腸活を効果的に進めるためには、発酵食品と食物繊維をうまく組み合わせて摂取することが大切です。おすすめの食材やメニューをご紹介します。
組み合わせの例)
● ヨーグルト+バナナ
ヨーグルトにバナナを加えて、朝食やおやつに。バナナの食物繊維とヨーグルトの乳酸菌を一緒に摂取できます(注7)。
● 味噌+きのこや海藻
味噌汁にきのこや海藻を加えることで、栄養価がアップ。きのこや海藻の食物繊維が加わり、満足感も得られます(注7)。
● 黒米もち麦ごはん×味噌
黒米もち麦ごはんに味噌汁を添えて。黒米ともち麦の食物繊維と味噌の乳酸菌が一緒に摂れる、簡単でおいしい組み合わせです。黒米もち麦ごはんを取り入れることで、白米よりも食物繊維量がアップします(注7)。
● ヨーグルト×レモン
ヨーグルトにレモンを加えて、さっぱりとした味わいに。おいしく、レモンの食物繊維とヨーグルトの乳酸菌を摂取できます(注7)。
● ラタトゥイユ×レモン×ヨーグルト
にんじん、トマト、玉ねぎなどの野菜をたっぷり使ったラタトゥイユは、栄養バランスの取れた一品です。さらに、レモンとヨーグルトをデザートに加えることで、爽やかな酸味とクリーミーな食感が楽しめます。また、ラタトゥイユはカレーとも相性が良く、カレーのルーにレモンとヨーグルトを加えることで、マイルドな酸味とコクが引き立ちます。
● ラタトゥイユ×黒米もち麦ごはん
ラタトゥイユをごはんに添えて。黒米やもち麦ごはんと合わせることで、食物繊維を豊富に摂れるだけでなく、もちもちした食感が楽しめます(注7)。
その他、発酵食品同士の組み合わせても、おすすめです。発酵食品は種類ごとに異なる菌を含んでいます。組み合わせることで相乗効果が期待でき、腸内環境を整えるだけでなく、味の深みも増して、食事の楽しみが一層広がります。
発酵食品同士の組み合わせ例)
● 納豆×キムチ
納豆とキムチを混ぜておかずの一品に。ごはんに乗せても、そのまま食べてもおいしくいただけます。
● 味噌×チーズ
味噌汁にチーズを加える、または味噌炒めにチーズを加えることで、発酵食品の相乗効果が得られます。
● 甘酒×りんご酢
甘酒にりんご酢を加えて、さっぱりとした飲み物に。甘酒の甘さとりんご酢の酸味がバランスよく、爽やかな風味が楽しめます。
● 甘酒×りんご酢×味噌
甘酒、りんご酢、味噌を加えてカレーを作ることも可能。甘み、酸味、旨味、辛みが調和したルーに仕上がり、腸活にも適した一品に。
6.腸活を支えるために気を付けたい生活習慣
腸内環境は食事だけでなく、生活習慣にも大きく影響します。腸活を支えるために、以下の生活習慣にも気を付けましょう。
● 偏った食事
動物性タンパク質や脂っこい食事が腸内環境に悪影響を与えることがあります。
● 運動不足
運動不足は腸の動きを鈍らせ、便秘や腸内環境の悪化を引き起こすことがあります。適度な運動を取り入れ、腸内の健康をサポートしましょう。
● 睡眠不足・ストレス
睡眠不足やストレスも腸内環境に影響を及ぼすことがあります。良質な睡眠を取り、ストレスを管理することが大切です。
7.まとめ
腸内環境を整えるためには、発酵食品と食物繊維を積極的に摂取することが重要です。また、生活習慣にも注意を払い、腸内環境のバランスを整える環境を作ることが健康維持に繋がります。腸活を日常生活に取り入れ、内側から健康をサポートしましょう。















